
100-FUKUSHIMA vol.085
郡山市医療介護病院 院長 原寿夫さん
医療と介護をつなぐ病院
紅葉で染まった中庭から、平坦なアプローチが敷地内の東屋に続いています。
「制度が変わり、現在は使われていないのですが、開院当初は、外の敷地もリハビリにも使ってもらえるようにと設置されました。院内には、長期の療養からご自宅に戻られる時、これまでの暮らし方と異なってもご自身やご家族でできることを確認して、ご自宅の生活に戻れるよう、退院前にご家族で数日宿泊できる台所を備えた和室があります」
郡山市医療介護病院、院長で内科医の原寿夫さんがそう教えてくれました。
郡山市医療介護病院は、高齢者を中心とした長期療養を必要とする方への医療と介護の提供、長期療養が必要な要介護者に対する介護医療院があり、一般の外来診療では地域の初期診療を担う公設民営の病院です。
診療は、医療支援か介護支援かが見極められ、その状況によって必要とする分野が変わった時にも対応しています。
開院した2006年当時は、全国で初めての医療と介護の両方を備えた病院でした。
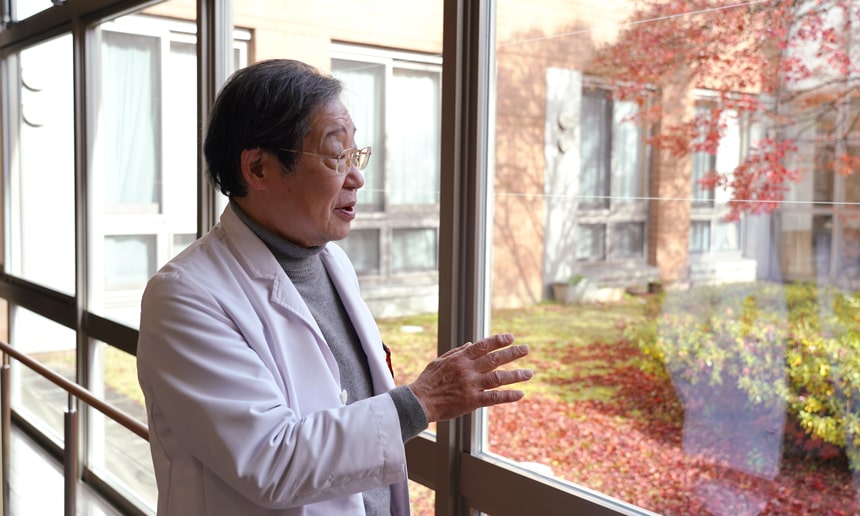
「私は素直に医者になることを希望していたわけではなく、病気そのものへの興味よりも、ちょっと違うところにありました。演劇や文学を好み、高校時代は安部公房の小説や演劇を観ていました。予定調和ではない実験的な演劇から、人生もそういうものだと感じ、明日のことは誰にもわからないから、今を生きることができる、だからその時間を互いに大事にすることに意味があるでのはないかと思っています。演劇で農村医学を広めた長野県の佐久総合病院でご活躍された若月俊一先生からも、医療と演劇、地域医療についての考え方も重なり、このふたりに憧れていたところがありました。そんなところから、自分もなにかしたいと思うようになりました」
三春町出身の原さんは、郡山市医療介護病院の院長職に就く以前、お父様が開業した原内科医院の医師として働いていました。お父様が50代で急逝されたことで、有床診療所であった医院を引き継ぎましたが、医療がさまざまに経過していく中で、有床診療所のあり方に疑問があったと話します。その一方で、医師会の仕事として、地域に関わり健診から予防を行っていくことに興味を持って仕事をするようになったと話します。
大学時代に、コンピュータを得意とする数学の教授のもとで、プログラミングを学び、卒業後、地元に戻ったのは、1982年の老人保健法が発足する時期と重なりました。
高齢者の健康保持、医療の確保を図るために病気の予防、治療、機能訓練などの保健事業を行って、国民の保健の向上と老人福祉の増進を図ることを目的とした老人保健法。その制定により創設された老人保健制度は、市町村が主体となって、高齢者と一定の障害者に対して、医療と保健サービスを提供するものでした。
「郡山市の健診データがあるもののそれをどうしていけばよいのか、まだわからないという状況だったため、郡山市と郡山医師会とで、地域ごとに集計をしてみましょうということになりました。当時はまだ『地域医療』という考えが明確ではありませんでした。私の方で健診データを分析し、この地域は貧血が多い、この地域は血圧が高いなど市の保健師さんに分析結果を返して、保健指導を行ってもらいました。そこから医師会の仕事をさせていただくようになりました」
原さんは、当時出席した学会で、法学、社会科学、宗教などの分野の方とこれから迎える高齢社会について話す機会があったことで、介護や在宅医療に興味を持つようになります。
「日本で介護保険を検討し始めた時は、ドイツがスタートして間もない頃で介護の分野のみで始まり、医療との繋がりがほとんどありませんでした。けれどスタートしてみたら、医療との関係を無視することができなかったのです。そこから日本ではもっと介護と医療が連携していくことを考え、今の制度になった経緯があります。その後、2000年に介護保険が始まり、当時日本医師会や厚生省の委員会に参加し、介護保険の立ち上げに携わりました。老人保健法、介護保険法という制度の変わり目に関わらせていただいたことをきっかけに、この病院に来ることになりました」
開院当時のスタッフは、医療と介護の分野半分ずつの割合であちこちの病院から集められました。原さんは、患者さんや利用者にとっては医療も介護も「ケア」であることに変わりはないため、スタッフには同じ方向を向いてもらいたいと月に一度必ず、病院が目指して取り組んで行くことをみんなで考えていこうと話しています。

「真空管のアンプでジャズを聴きながら、ラフロイグウィスキーの飲むのがストレス解消法。オーディオはラックス、クラシックではブラームスが好きで、ストラヴィンスキーのリズムがこころに染みるようになり、そこからジャズを聴くようになりました」
スタッフも患者さんも、自身の人生を振り返ることで、
残りの時間を豊かなものにする
治療から看取りまでを行う郡山市医療介護病院で、原さんは人が病気になることや亡くなるということに慣れてはいけないと話します。
「長く医療に携わりながら、慣れちゃいけないという思いがあります。例えば、認知症の方に接する時。家族であれば感情的な面でなかなかに耐え難い場面があります。私たちが業務として、認知症の方に関わるなら、優しさを伝える技術を持って業務にあたってほしいとスタッフに伝えています。業務に感情は入らないのです。感情が入ると嫌なことに対してこちらも嫌な反応で返してしまいますが、技術としてものごとが捉えられれば、客観性を持って状況を判断して、話を逸らしてみるなど対応することができます」
郡山市医療介護病院では10年前から、認知症の方へ優しさを伝えるケア技法「ユマニチュード」に取り組んでいます。
ユマニチュードとは、フランスで生まれた知覚・聴覚・触覚などを用いたコミュニケーションに基づく技術、認知症の方へのケア技法で、病院スタッフは入職時の基本研修、その後ステップアップのための研修にも定期的に参加しています。
原さんは医療と介護の技術に加えて、自身の人生を振り返る時間がスタッフと患者さんのどちらにも大切なことだと話されます。
「五木寛之の小説に『林住期』というものがあります。学ぶ時期の学生期、学んだことを社会にでて還元し家庭を持つ家住期、自分の人生を振り返り残りの人生を考える林住期、あとは好きなことをしてよいとする遊行期という、インド哲学による人生を4段階にわけた考えです。今互いにどの時期にいるのかがわかると、日々感情がぶつかることを少なくしていけると思っています。スタッフには技術を持つことと一緒に、自身の人生を俯瞰的に見ることも大切です。できれば患者さんにも、これからお茶をしにいこう、なにかしようと自分で選択し、行動ができるうちに、ご自身の人生を振り返る時間をつくってもらえたら、残りの人生を豊かなものにできるんじゃないかなと思っています」
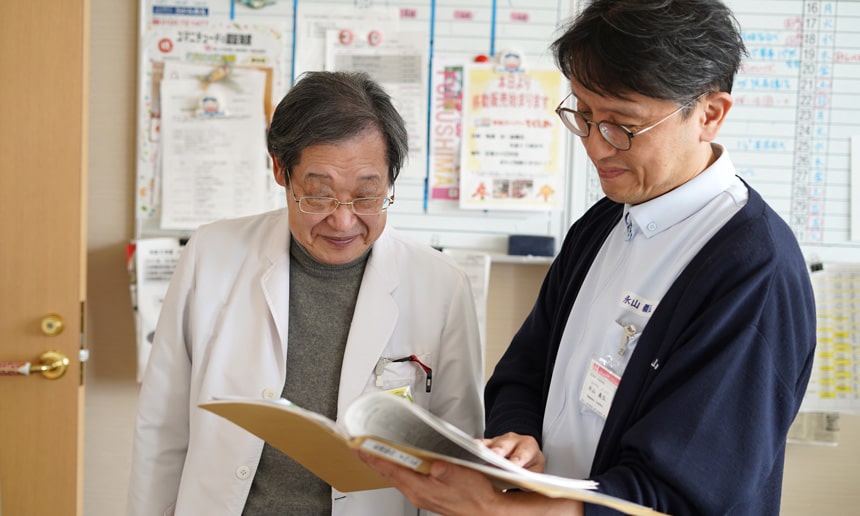
その方とご家族が幸せで安心できること
家族や身近な人が認知症になった時、長い治療や介護が必要になった時、本人はもちろん、そばにいるご家族にとってもままならない日々が続くことがあります。そうした日々に、どうすればお互いに安心を得ることができるのかを尋ねました。
「研修でユマニチュードを提唱する先生が来られた時、先生は、患者さんの生活歴を詳しく伺っていました。なぜそうするのか尋ねると、どのような仕事をして、どのような生活を送ってきた人なのかを知ることは、その方の考えを知ることでもあるということがわかりました。その方がお元気な時に一生懸命されていたことが、認知症になった時に振り返ることだったりします。毎朝忙しく食事の準備をしていた主婦の方は、認知症になった時、朝方に気持ちが不安定になることがあります。同じ時間になると、なにかしなければと思い、行動しようとするけれどうまくやれないという状況がそうさせてしまうようでした。その方がやりたいと思って、一生懸命やっていたことを、再現できる場を作ってあげることが、今のその方の充足感になり、まわりの安心につながるのだと思います。この薬を飲めば安心できるという対処ではなく、その方の生活に合わせた場の設定が大事かなと思っています」
原さんが話す「場」とは、家庭生活や仕事、趣味といった自分が活躍する場のことで、元気な時にはいくつもあった場は、年を重ねるとその数が減っていくといいます。
「現役から引退すると、どうしても仕事が減っていったり、子どもが独立すれば、昔ほど買い物や出かける回数も減り、場合によっては家の中だけで過ごすようになって、場が家だけになるかもしれません。場の数を戻すにも、ただ数を増やすのではなく、その方が一番大切にして、楽しいと思っていたときの場を設定することが大事です。もし晩酌が好きな方ならば、私はたとえ入院中であっても、誕生日など特別な日だけでも晩酌を認めてもいいのではないかと、個人的には思っています。その方が一番楽しくて、よかったなと思う時の過ごし方をみんなでサポートする、それがその方の幸せになり、まわりにとっても安心なことにつながっていくのだと思います」

「『みんなで考えませんか?』認知症になっても希望をもって安心して暮らせる街」にて。
病院の考えや取り組みから、地域のこれからの暮らしに「安心」を考える公開講座を開催しています。
自分たちの技術で、郡山をやさしい街に
「地元の民間の人たちが力を合わせて、街づくりをしてきたのが郡山だと思います。白河藩、二本松藩、会津藩の間、あまり特徴がなかった郡山で、明治以降に人の往来があり、民間で医療機関を作って、自分たちの町と暮らしを自分たちで守っていこうという闊達さがあったのだと思います」
原さんは、郡山の医療機関の充実についてそう話されます。
「『継続は力なり』という言葉が好きで、開業医から郡山でさまざまな仕事や現場も変わってきましたが、やりたいことを続けてきました。基本的に人が好きで、地域が好きで、そこに関わる仕事がしたいという気持ちに変わりありません。私の仕事は、その方の目指す幸せをサポートするものだと思います。医療はそのための手段です。ものと技術の開発が繰り返されて、医学の進歩がありますが、そこには患者さんの生活や心の部分は傍に置いてあります。ただ感染症の場合は、殺菌する薬の開発も必要ですが、その人の考えや行動パターンが大きく影響してくるので、かつて感染症が流行した時のように、もう一度人の動きや考えを取り入れた治療を検討しなければならないと感じています。そこにその方の幸せを、自分たちが持っている技術でどうサポートできるのかを考えることが私たちの仕事なのだと思います」
原さんは、郡山市医療介護病院が長年取り組んできたユマニチュードの技術を、これから地域に広げていくことを希望しています。
「ユマニチュードはケアの技術ではありますが、これは私たちの普段の暮らしでも応用できることだと思います。地域でやさしさを伝えあってもらえたら、子どもたちからお年寄りまで笑顔が絶えない街になり、なにも心配はいらないと思っています。以前、実験として、大学の学生に駅から市役所や公民館まで車椅子で移動をしてもらったことがありました。結果は、公的機関の間、平坦と思われる道であっても、移動が大変になるというものでした。ヨーロッパの古い石畳の街では、困っている人がいれば、その様子からだれかが声をかけ、助けてくれることが日常にあり、車椅子の移動もそれほど難しくはないといいます。そうしたことからも、点字ブロックがある、スロープがあるというハード面だけで『やさしい街』になるわけではなく、その時の状況に応じて、声をかけてくれる人がいることで『やさしい街』になっていくのだと思います」
—
一般社団法人 郡山医師会 郡山市医療介護病院
http://bigheart-hp.net/
福島県郡山市上亀田1−1
024-934-1240
診療時時間 9:00-12:00(午前のみ)
休診日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
2024.12.09 取材 文:yanai 写真:BUN



